「就職氷河期は一体、誰のせいだったのだろうか…」もしあなたが今、そう感じて原因を深く知りたいと思っているなら、この記事がその答えを導き出す一助となるでしょう。この問題は、単に景気が悪かったという一言で片付けられるものではなく、当時の日本の社会構造そのものが複雑に絡み合って生み出したものです。
この記事では、まず「就職氷河期は誰のせいなのか」という問いに対し、社会構造の側面からその原因を丁寧に紐解いていきます。具体的には、「就職氷河期の原因は何ですか?」という根源的な疑問から始め、「就職氷河期は一体誰が作ったのか」、そして「就職氷河期で一番ひどい年はいつだったのか」を、信頼できるデータと共に深く掘り下げて解説します。
さらに、「結局、就職氷河期は何が問題だったのか」を多角的に分析し、当時の「民主党政権と就職氷河期世代の関係性」にも光を当てます。記事の後半では、「就職氷河期は誰のせいか」という視点を保ちながら、この世代が受けた深刻な影響と厳しい現実に焦点を移します。「就職氷河期世代の現在の年齢層」や、特に過酷な状況に置かれた「超氷河期世代とは何年生まれの人々か」を明確にします。
また、見過ごされがちな「就職氷河期世代の女性が持つ特徴」や、逆境の中で生まれた「就職氷河期世代は優秀だという説」の背景、そして多くの人が抱く「なぜ氷河期世代は見捨てたと言われるのか」という感情の根源を探ります。最後に、この記事の結論として、「就職氷河期は誰のせいか」、そして社会全体が今まさに支払わされている「見捨てたツケ」を考察し、この根深い問題の全体像を明らかにします。
- 就職氷河期が生まれた社会的な背景
- 世代が直面した具体的な問題点
- 政府や企業の対応とその影響
- 就職氷河期世代の現状と今後の課題
就職氷河期は誰のせい?社会構造から紐解く原因
- 就職氷河期の原因は何ですか?
- 就職氷河期は一体誰が作ったのか
- 就職氷河期で一番ひどい年はいつ?
- 結局、就職氷河期は何が問題だったのか
- 民主党政権と就職氷河期世代の関係性
就職氷河期の原因は何ですか?
就職氷河期の引き金を引いた最大の原因は、疑いようもなく1990年代初頭に発生したバブル経済の崩壊です。土地や株価といった資産価格が実体経済と乖離して異常に高騰したバブル経済が弾けたことで、日本経済は「失われた20年」とも呼ばれる長く深刻な不況のトンネルへと突入しました。
この経済の急激な冷え込みを受け、多くの企業は深刻な経営不振に陥りました。生き残りをかけて財務体質の改善を迫られた企業が、最も手っ取り早いコストカット策として着手したのが、人件費の抑制、とりわけ新卒採用の大幅な削減だったのです。
バブル絶頂期には、一人の学生の内定先が複数あるのが当たり前で、企業が学生を接待漬けにするほどの売り手市場でした。しかし、その状況は一変します。企業の採用意欲は急速に凍りつき、この社会構造の激変が、まさに社会に出ようとしていた若者たちを容赦なく直撃したのです。これが、就職活動を極めて困難なものにした根本的な要因です。
就職氷河期を生んだ3つの主要因
- バブル崩壊による長期経済不況: 日本経済全体の成長が止まり、企業の投資意欲や採用意欲が完全に失われました。不良債権問題の処理が遅れたことも、不況を長引かせる原因となりました。
- 企業の防衛的な採用抑制: 多くの企業が、既存の従業員(特に中高年層)の雇用を守ることを優先し、そのための調整弁として新卒採用の枠を極端に絞りました。
- 非正規雇用の規制緩和: 後述しますが、2000年代の労働法制の変更が、企業にとって正社員を雇うインセンティブをさらに低下させ、非正規雇用への置き換えを加速させる一因となりました。
このように、就職氷河期は一個人の努力や能力の問題では決してなく、経済の地殻変動という、抗いようのない巨大な波によって引き起こされた深刻な社会問題であったと言えます。
就職氷河期は一体誰が作ったのか
就職氷河期という特異な状況を「誰か特定の人物や組織が意図的に作った」と断定することはできません。この問題は、特定の誰かの悪意によるものではなく、当時の経済状況、旧来の雇用慣行に固執した企業、そして時代の変化に対応しきれなかった政府の政策など、複数の要因が不幸な形で連鎖して生まれた「構造的な問題」だからです。
直接的な引き金はバブル崩壊ですが、問題の本質はその後の社会の対応にありました。多くの日本企業は、解雇規制が厳しい「終身雇用」を前提とした雇用システムを維持していました。そのため、不況下で人件費を調整する必要に迫られた際、既存の正社員を解雇するのではなく、入り口である新卒採用を止めるという安易な手段に頼ったのです。
この流れを決定的にしたのが、2000年代初頭の小泉政権下で進められた「聖域なき構造改革」の一環である労働者派遣法の改正(2004年)です。それまで専門職などに限定されていた労働者派遣が、製造業の現場へも解禁されました。これにより、企業は人件費が固定化される正社員を雇う代わりに、景気変動に応じて容易に調整できる安価な労働力として非正規雇用を積極的に活用する道を選んだのです。
厚生労働省の当時の審議会資料にもあるように、この規制緩和は雇用の流動性を高め、国際競争力を強化するという目的を掲げていました。しかし、その結果として正社員の雇用機会が大幅に失われ、非正規雇用が社会に広く定着する構造転換を招いてしまった負の側面は、決して無視できません。
特定の誰かを「犯人」として糾弾するよりも、バブル後の経済危機という国難に対し、社会全体、特に意思決定を担う企業や政府が、痛みを若者という最も弱い立場に集中させる形で対応してしまった。その結果として「就職氷河期」という犠牲の世代が生まれてしまった、と理解するのがより本質的でしょう。
ある意味では、バブル世代以上の安定した雇用を守るための「防波堤」や「安全弁」として、氷河期世代が社会的に利用されたという厳しい見方も成り立ちます。
就職氷河期で一番ひどい年はいつ?
就職氷河期は、1993年頃から2005年頃まで約10年以上にわたって続いた長い期間です。その中でも、状況が極度に悪化し、まさに「氷河期の底」と呼べるほど深刻だったのは、1999年(平成11年)から2000年代初頭にかけての時期でした。
この時期の惨状は、当時の経済指標、特に学生の就職状況を如実に示す有効求人倍率のデータから明確に読み取れます。バブル期には2倍を超え、学生優位だった大卒有効求人倍率は、坂道を転げ落ちるように下落していきました。
そして1999年、大卒の有効求人倍率はついに0.99倍となり、統計を取り始めて以来、史上初めて1倍を割り込むという衝撃的な事態に陥りました。これは、就職を希望する学生全員分の求人が、社会に存在しないことを意味します。つまり、どれだけ優秀で努力をしても、構造的に誰かが必ず就職できないという、あまりにも過酷な現実を若者たちに突きつけたのです。
状況はさらに悪化し、翌年の2000年には、求人倍率は0.48倍という歴史的な低水準にまで落ち込みました。これは、単純計算で「2人の学生が、たった1つの求人枠を奪い合う」という凄惨な状況であり、まさに「氷河期」を象徴する数字と言えるでしょう。この背景には、1997年のアジア通貨危機や、山一證券、北海道拓殖銀行といった大手金融機関の相次ぐ経営破綻があり、日本経済全体が先行きの見えない深い闇に包まれていたことが挙げられます。
有効求人倍率(大卒)の推移に見る氷河期の深刻さ
| 年(3月卒業者) | 有効求人倍率 | 主な出来事 |
|---|---|---|
| 1991年 | 2.86倍 | バブル景気のピーク |
| 1993年 | 1.91倍 | 就職氷河期の始まり |
| 1999年 | 0.99倍 | 史上初の1倍割れ |
| 2000年 | 0.48倍 | 氷河期の底・過去最低水準 |
| 2009年 | 0.47倍 | リーマンショックの影響 |
後のリーマンショック時にも同水準まで落ち込みましたが、就職氷河期問題の根深さは、この絶望的な低水準が単発ではなく、長期間にわたって継続した点にあります。一度キャリアのスタートでつまずくと、挽回のチャンスがほとんど与えられない硬直的な社会構造の中で、多くの若者が希望を失い、キャリアの第一歩を踏み出せないまま苦しみ続けることになったのです。
結局、就職氷河期は何が問題だったのか
就職氷河期の最大の問題点は、単に「求人が少なくて就職が大変だった」という表面的な現象だけではありません。その本質は、日本特有の硬直的な「新卒一括採用」という雇用システムと、一度レールを外れた者に対するセーフティネットの欠如にあります。
当時の日本企業では、正社員になるためのルートが、高校や大学を卒業するタイミングでの「新卒採用」にほぼ限定されていました。この「一度きりの切符」を逃してしまうと、その後の人生で正社員になる道は極めて険しいものになりました。一度、非正規雇用や無職の期間を経験すると、「新卒」という最強のカードを失うだけでなく、中途採用市場では「職務経験なし」と見なされ、年齢だけを重ねた不利な存在として扱われてしまったのです。
就職氷河期世代を追い詰めた構造的な問題点
- 新卒一括採用への過度な依存: 卒業時のワンチャンスを逃すと、正規雇用のキャリアパスから弾き出され、再挑戦が非常に困難でした。
- 年功序列とメンバーシップ型雇用: スキルよりも年齢や勤続年数が重視されるため、未経験の中途採用者に門戸が開かれていませんでした。企業は「まっさらな新卒」を自社色に染めることを好んだのです。
- キャリアアップの機会の欠如: 一度非正規雇用になると、そこからスキルを磨いて正社員へとステップアップするための社会的な仕組みや、企業の受け皿がほとんど存在しませんでした。
つまり、本人の能力や意欲とは無関係に、社会に出るタイミングが数年ずれただけで、その後の人生設計が根底から覆されてしまうという構造そのものが、就職氷河期世代を苦しめ続けた最大の要因なのです。後に景気が回復局面を迎えても、年齢を重ねてしまった未経験者を採用しようとする企業はごく少数でした。その結果、多くの人々が不安定な雇用のまま固定化され、社会から取り残されることになったのです。これは紛れもなく、個人の「自己責任」ではなく、社会システムの欠陥であったと言えるでしょう。
民主党政権と就職氷河期世代の関係性
就職氷河期という長期にわたる問題の中で、特定の政権がどのような政策を打ち、それが世代にどう影響したかを検証することも重要です。非正規雇用拡大の扉を開いたのが2000年代初頭の小泉政権であったことは前述の通りですが、その後の政権の対応もまた、世代の運命を左右しました。
特に、リーマンショック後の世界的な経済危機の中で誕生した民主党政権(2009年〜2012年)時代の政策は、その意図とは裏腹に、結果として氷河期世代の状況を好転させるには至らなかった、という厳しい指摘があります。当時、「年越し派遣村」に象徴されるように、非正規労働者の雇い止め(派遣切り)が深刻な社会問題となり、世論は派遣労働に対する厳しい目を向けていました。
こうした社会的要請を受け、民主党政権は労働者保護を前面に掲げ、派遣労働の規制を大幅に強化する方向へと舵を切りました。具体的には、製造業への派遣を原則禁止するなど、企業が派遣労働を利用しにくくする法改正を進めたのです。
この政策は、派遣労働者の劣悪な待遇を改善し、直接雇用を促すという崇高な目的を持っていました。しかし、経済界からは「雇用の柔軟性が失われる」と強い反発を受け、企業側の行動は政権の思惑とは異なる結果を招きました。多くの企業は、コストの上がる派遣社員を正社員として直接雇用するのではなく、より雇用調整が容易でコストも低いパートタイムやアルバイトといった、さらに不安定な雇用形態に切り替えるか、あるいは採用そのものを見送るという選択をしたのです。
この一連の動きは、「政策の意図とは裏腹に、かえって不安定な雇用を増やし、失業者を増加させたのではないか」という批判を生むことになりました。就職氷河期世代の中には、派遣という働き方で専門的なスキルを地道に積んできた人々もいましたが、規制強化によってその働き口すら失ってしまうという、皮肉な結末を迎えたケースも少なくなかったかもしれません。
もちろん、これはあくまで多角的な視点の一つです。未曾有の経済危機の中での政策決定は極めて難しく、どの選択が唯一の正解だったかを後から断じることは困難です。しかし、結果として、就職氷河期世代が切望した雇用の安定と生活の安心にはつながらなかった、と感じた人々が多かったことは、紛れもない事実と言えるでしょう。
就職氷河期は誰のせい?世代が受けた影響と現実
- 就職氷河期世代の現在の年齢層
- 超氷河期世代とは何年生まれの世代か
- 就職氷河期世代の女性が持つ特徴
- 就職氷河期世代は優秀だという説を解説
- なぜ氷河期世代は見捨てたと言われるのか
- 就職氷河期は誰のせいか?見捨てたツケを考察
就職氷河期世代の現在の年齢層
一般的に「就職氷河期世代(ロストジェネレーション)」とは、バブル経済崩壊後の雇用環境が著しく悪化した1993年(平成5年)頃から2004年(平成16年)頃に学校を卒業し、社会人となった世代を指します。この定義は政府の支援策などでも用いられており、内閣官房の就職氷河期世代支援推進室のサイトでも同様の期間が示されています。
この定義に基づき、2025年時点での就職氷河期世代の年齢を計算すると、おおむね40代前半から50代前半という、社会や家庭において中核を担うべき年齢層に該当します。
就職氷河期世代の年齢(2025年時点)
- 1993年に大学を卒業した人(1970年度生まれ): 満54歳~55歳
- 2004年に大学を卒業した人(1981年度生まれ): 満43歳~44歳
※高卒や専門学校卒の場合は、これより若い年齢層も含まれます。
特筆すべきは、この世代が日本の人口構成の中で最もボリュームが大きい「団塊ジュニア世代」(1971年~1974年生まれ)と大部分が重なっている点です。ただでさえ母数が多く競争が激しい世代であったにもかかわらず、企業の採用枠が歴史的に最も絞られるという、「人口の波」と「経済の谷」が不運にも重なった二重の苦しみを味わうことになりました。
現在、この世代は多くの組織で管理職などに就く年齢に達していますが、一方で、キャリアのスタート地点でつまずいた影響から、今なお非正規雇用のまま不安定な生活を送る人も少なくありません。40代、50代になっても経済的な基盤を確立できず、自身の老後や親の介護といった問題に直面し、将来への深刻な不安を抱えているケースが多いのが、この世代が直面する厳しい現実です。
超氷河期世代とは何年生まれの世代か
「超氷河期世代」という言葉は、長く続いた就職氷河期の中でも、特に状況が悲惨を極めた最悪の時期に就職活動を強いられた人々を指す俗称です。これは正式な定義ではありませんが、一般的には大卒有効求人倍率が史上初めて1.0倍を割り込み、歴史的な底を記録した1999年〜2004年頃に学校を卒業した世代を指す場合が多いです。
この期間に大学を卒業した人々の生まれ年を考えると、おおよそ1976年(昭和51年)から1981年(昭和56年)生まれの人々が、この「超氷河期世代」の中心となります。彼らは、社会に出る最初のステップで、自身の能力や努力とは無関係に、極めて理不尽で不平等な競争を強いられました。
「2人で1つの椅子を奪い合う」どころか、それ以上の過酷な状況も珍しくありませんでした。何十社、百社以上に応募しても内定が一つも得られない学生が続出し、多くの若者が心を折られ、不本意ながら非正規雇用の道を選ばざるを得なかったのです。この時期にはITバブルの崩壊(2000年)も重なり、まさに泣きっ面に蜂の状態でした。
この世代は現在、40代半ばから後半に差し掛かっており、政府が打ち出している就職氷河期世代支援策においても、特に深刻な課題を抱える層として、重点的なサポートが必要だと認識されています。キャリアを通じて一度も正社員として働いた経験がない人や、長期にわたり社会との接点を失ってしまった「ひきこもり」状態にある人も少なくなく、就職氷河期問題の根深さを最も象徴する世代と言えるでしょう。
就職氷河期世代の女性が持つ特徴
ただでさえ過酷だった就職氷河期は、特に女性にとって、より一層厚く、冷たい氷壁として立ちはだかりました。その背景には、当時の日本社会にまだ色濃く残っていた根強い男女の役割分業意識や、企業の採用活動における構造的な差別が存在したからです。
就職氷河期という困難な時代を経験した女性たちには、以下のような共通の特徴や課題が見られることがあります。
1. 圧倒的に高い非正規雇用の割合
企業の採用抑制が本格化した際、真っ先に削減の対象となったのが女性の採用枠、特に一般職の採用でした。多くの企業がコストカットのために「お茶くみ」や「コピー取り」と見なされがちだった一般職の採用を停止、あるいは大幅に削減したため、多くの女性が正社員としての就職を断念せざるを得ませんでした。その結果、同世代の男性と比較しても、非正規雇用(派遣、パート、アルバイト)の割合が著しく高いという統計的な傾向があります。
2. 深刻な経済的自立の困難さ
非正規雇用は、ご存知の通り収入が不安定で低く、ボーナスや退職金もなく、昇給の機会もほとんどありません。キャリア形成にもつながりにくいため、経済的に自立して生涯を設計することが極めて困難になります。この経済的な不安定さが、同世代の未婚率・非婚率の高さに直結し、結果として日本の少子化を加速させる大きな一因ともなりました。
当時はまだ「女性はどうせ結婚して辞めるだろう(寿退社)」という企業の勝手な思い込みや偏見がまかり通っていました。高い能力や意欲があっても、性別というだけで正社員への道が閉ざされた女性が数えきれないほどいたのです。キャリアを築きたくても、そのスタートラインにすら立つことを許されなかった理不尽さは、計り知れません。
3. ポテンシャルとキャリアの断絶
本来持っている高い能力や学歴に見合った職に就くことができず、不本意なキャリアを歩んできた人も非常に多くいます。高いポテンシャルを持ちながら、それを十分に発揮する機会に恵まれなかったことは、もちろん個人にとっての悲劇ですが、同時に労働力不足が叫ばれる日本社会全体にとっても、取り返しのつかない大きな損失であったと言えるでしょう。
就職氷河期世代は優秀だという説を解説
就職氷河期世代は、とかく「不遇」や「悲劇」の世代として語られがちです。しかしその一方で、逆説的ですが「厳しい時代を生き抜いてきたからこそ、実は優秀な人材が多い」という説も根強く存在します。これは決して精神論や同情論ではなく、いくつかの合理的な理由に基づいています。
1. 熾烈な競争を勝ち抜いたサバイバル能力
まず、正社員として就職できた人々は、歴史上類を見ないほど少ない採用枠を巡って、膨大な数のライバルとの熾烈な競争を勝ち抜いてきた、文字通りのサバイバーです。エントリーシートの書き方から面接対策まで、自ら徹底的に考え抜き、行動しなければ内定を得られなかった経験は、彼らの基礎的なビジネススキルや問題解決能力を極めて高いレベルに引き上げました。
2. 高いストレス耐性と強靭な自律性
理不尽な環境下でキャリアをスタートさせた経験は、彼らに強靭な精神力をもたらしました。会社の庇護や終身雇用を安易に期待できず、常に自分の力で道を切り拓くしかないという現実に直面してきたため、他責にせず、自律的に思考し、主体的に行動する能力や、少々のことでは動じないストレス耐性が自然と培われている傾向があります。
この「優秀説」は、運よく正社員になれた層だけに当てはまるものではありません。非正規雇用という逆境から這い上がり、専門スキルを磨いてキャリアアップを果たした人や、組織に頼らず自ら起業の道を選んで成功した人も数多く存在します。逆境をバネにしてきた経験そのものが、彼らをより強く、実践的な能力を持つ優秀な人材へと成長させた側面は間違いなくあるのです。
3. 優れた危機管理能力と現実主義
常に雇用の不安定さや会社の倒産リスクと隣り合わせで社会人生活を送ってきたため、危機管理能力が非常に高いとも言われます。会社の業績や社会情勢の変化に敏感で、楽観的な見通しに頼らず、常に最悪の事態を想定して「次の一手」を考えて行動する習慣が身についている人も少なくありません。この現実主義的な視点は、現代の不確実なビジネス環境において極めて価値のある能力と言えるでしょう。
もちろん、これらの特徴が世代全体に当てはまるわけではありません。しかし、あまりにも過酷な外部環境が、結果としてこの世代の人材を非常にタフで、実践的なスキルを持つ優秀な層へと鍛え上げたという見方は、十分に説得力を持っています。
なぜ氷河期世代は見捨てたと言われるのか
多くの就職氷河期世代が、社会から「見捨てられた」という深い孤立感や憤りを抱いています。この感情は単なる被害者意識から来るものではなく、彼らが最も困難な状況に直面している間、社会、政府、そして企業が、見て見ぬふりを続け、問題を長期間にわたって実質的に放置してきたという厳然たる事実に基づいています。
具体的には、社会の各主体が以下のような対応を取ったことが、「見捨てられた」という感覚を醸成しました。
- 企業の自己保身: 多くの企業は、バブル期に大量採用した中高年社員の雇用と高い給与水準を維持することを最優先しました。そのためのコスト削減の矛先は、まだ組織の一員ですらない、これから社会に出る若者たちに向けられました。これは、既存社員の生活を守るために、未来への投資である若者を犠牲にするという、世代間の利害対立の構図でした。
- 政府の対応の致命的な遅れ: 就職氷河期が深刻な社会問題として認知されてからも、政府による本格的な支援策は驚くほど遅々として進みませんでした。当時の社会には「努力が足りないから就職できないのだ」という「自己責任論」が根強く、公的な資金を投じて彼らを支援するという社会的合意がなかなか形成されなかったのです。政府がようやく重い腰を上げたのは、この世代が40代に差し掛かり、将来の社会保障制度の担い手不足や、生活保護受給者の急増が現実的な脅威として認識され始めてからでした。
- 労働組合の沈黙と機能不全: 企業の内部組織である日本の労働組合は、組合員である正社員の雇用と権利を守ることには熱心でしたが、組織の外にいる若者や、急増する非正規雇用者の問題にはほとんど関心を示さず、有効な声を上げることはありませんでした。
このように、社会を構成する主要なプレイヤーたちが、それぞれの立場や組織の利益を守ることを優先し、世代間で痛みを公平に分かち合うことをせず、社会的に最も立場の弱い若者世代にすべての負担を押し付けたのです。この「社会全体からの無視」とも言える経験が、就職氷河期世代の心に深い傷を残し、拭い去ることのできない「見捨てられた」という感覚につながっているのです。
就職氷河期は誰のせいか?見捨てたツケを考察
この記事を通じて繰り返し見てきたように、就職氷河期は特定の誰か一人の責任によって引き起こされたものではなく、複合的な要因が絡み合って生まれた根深い社会構造の問題です。そして、この世代を社会全体で「見捨てた」ことによる巨大なツケは、20年以上の時を経て、今まさに日本社会全体に重くのしかかっています。
この「見捨てたツケ」は、具体的に以下のような形で社会に現れています。
- 深刻な少子化の加速: 経済的な不安定さから結婚や出産を躊躇、あるいは断念せざるを得なかった人々が非常に多く、これは日本の急速な少子化をさらに加速させる決定的な一因となりました。
- 日本経済の長期的な停滞: 本来であれば消費の中核を担うはずの世代に所得の低い層が多いため、個人消費が長期間にわたって伸び悩み、日本経済全体の長期的な停滞、いわゆる「失われた20年(30年)」の大きな要因となっています。
- 社会保障制度の崩壊リスク: 十分な所得を得られず、年金保険料を十分に納めてこなかった人々が多いため、この世代が高齢期に達した際、生活保護の受給者が急増し、年金・医療・介護といった社会保障制度全体が崩壊の危機に瀕するのではないかと強く懸念されています。
- 深刻な人手不足と技術継承の断絶: 本来、多くの企業で中核的な役割を担うはずだった世代に非正規雇用者が多いことで、組織内での円滑な技術やスキルの継承が阻害されています。これが、現在の深刻な人手不足問題の背景の一つにもなっています。
- 8050問題の顕在化: 80代の高齢の親が、社会から孤立しひきこもり状態にある50代の子どもの生活を支えるという「8050問題」も、その多くが就職氷河期世代の問題の延長線上にあり、社会的な孤立の深刻さを示しています。
結論として、「就職氷河期は誰のせいか?」という問いに対する最も的確な答えは、「特定の誰かではなく、バブル崩壊という未曾有の経済危機に直面した際、痛みの先送りを決め込み、未来を担うはずだった若者世代にその犠牲を不当に強いた、当時の社会全体の構造的な責任である」と言えるでしょう。そして、その時に見て見ぬふりをされた問題が、時を経てより大きく、より深刻な課題となって、今の日本社会に重く突きつけられているのです。
【最終まとめ】この記事のポイント
- 就職氷河期の直接的な原因はバブル崩壊による未曾有の経済不況
- 企業は既存社員の雇用を守るため未来への投資である新卒採用を大幅に抑制
- 政府による非正規雇用の規制緩和が、結果として正社員への道をさらに狭めた
- 最も就職環境が厳しかったのは1999年から2000年代初頭にかけて
- 有効求人倍率は一時0.5倍を割り込み、2人で1つの求人を奪い合う異常事態だった
- 問題の本質は、一度失敗するとやり直しが効かない新卒一括採用という日本独自の雇用システムにある
- 一度正規雇用のレールから外れると、スキルがあっても正社員として復帰するのが極めて困難だった
- 就職氷河期世代は現在40代前半から50代前半が中心であり、団塊ジュニア世代と重なる
- 特に困難だった超氷河期世代は、1976年(昭和51年)から1981年(昭和56年)生まれが該当する
- 女性は構造的な差別もあり、非正規雇用の割合がより高く、経済的自立が困難なケースが多い
- 過酷な競争を生き抜いた経験から、ストレス耐性が高く優秀な人材が多いという側面もある
- 社会全体が問題を放置し、若者に負担を押し付けたことが「見捨てられた」という世代の感情を生んだ
- 氷河期世代の問題を放置した「ツケ」が、少子化、経済停滞、人手不足として現代の日本を苦しめている
- 将来の社会保障制度を揺るがしかねない、極めて大きな不安要素ともなっている
- この問題は特定の誰かのせいではなく、未来への責任を放棄した社会全体の構造的な責任である

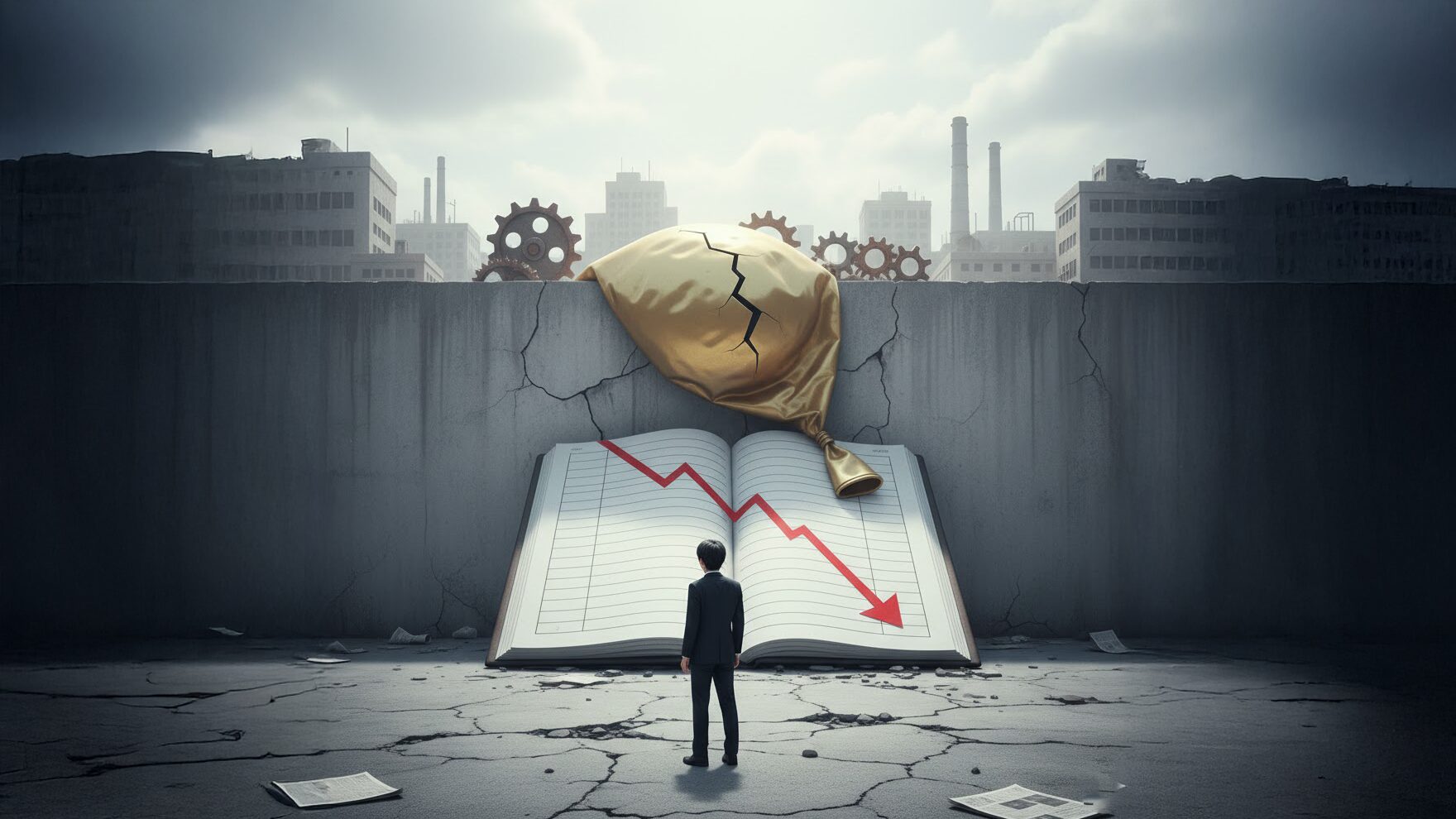


コメント